![[二十四節気]啓蟄:春の訪れを告げる虫たちの息吹](https://greenenishi.com/wp-content/uploads/2024/04/p1.jpg)
この記事はだいたい 3
分前後で読めます。
二十四節気のひとつ「啓蟄」は、3月5日頃に訪れる、春の訪れを告げる大切な節気です。
今回は、「啓蟄」についてご紹介いたします。
目次
Outline
啓蟄の意味・由来
啓蟄は3月5日頃に訪れます。
「啓」は「開く」という意味、「蟄」は「虫が冬の間土中に潜って冬眠する」という意味。
つまり「啓蟄」は、冬眠していた虫たちが土中から這い出し、活発に動き始める頃をいいます。
啓蟄の頃の気候
桜舞い散る陽光はまだ先だけれど、足元には確実に春の訪れを感じられる季節になりました。二十四節気の「啓蟄」は、まさにそんな季節の移ろいを感じる頃です。
七十二候
啓蟄には、七十二候と呼ばれる、さらに細かく季節を分けた三つの候があります。
蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく)
冬眠していた虫たちが土中から這い出てくる頃です。
桃始笑(ももはじめてさく)
桃の花がほころび始める頃です。
菜虫化蝶(なむしちょうとなる)
菜食の虫が蝶に変身する頃です。
啓蟄の年中行事や風習
啓蟄の頃の風習をご紹介します。
・お水取り
奈良・東大寺で行われる、二月堂の閼伽井戸(あかいど)からご神水(香水)を汲み上げる行事です。
![[二十四節気]霜降:秋から冬へ、季節の変わり目](https://greenenishi.com/wp-content/uploads/2024/11/pass-38-320x208.png)

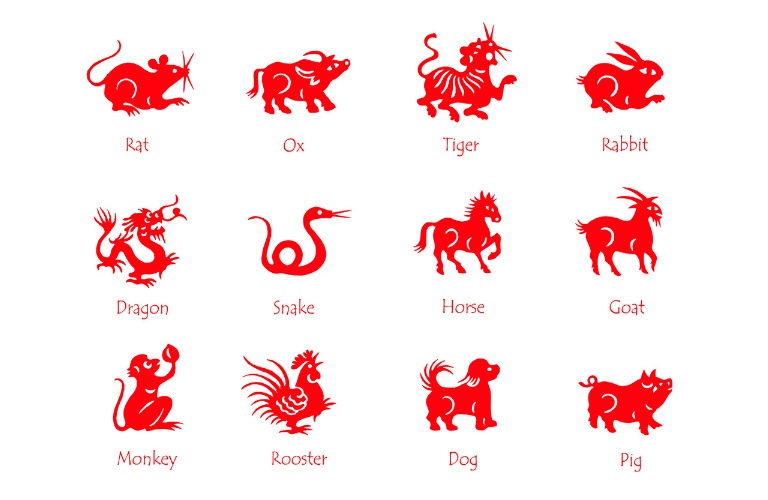


![[二十四節気]小寒:寒の入り本格的な冬の始まり](https://greenenishi.com/wp-content/uploads/2024/12/pass-44-320x208.png)
![[二十四節気]冬至:太陽が生まれ変わる日](https://greenenishi.com/wp-content/uploads/2024/11/pass-43-320x208.png)
![[二十四節気]大雪:本格的な冬の到来](https://greenenishi.com/wp-content/uploads/2024/11/pass-42-320x208.png)
![[二十四節気]小雪:わずかな雪が降る頃](https://greenenishi.com/wp-content/uploads/2024/11/pass-41-320x208.png)